
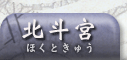
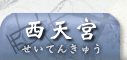
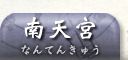

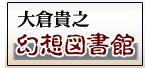
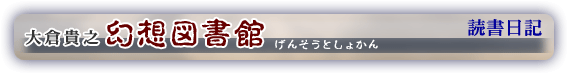
| 雑誌編 |
|
かなりマニアックなジャンルおよび趣味であっても、たいていは専門誌があり驚かされることがあります。なぜ驚くかといえば、それは自分に興味がない範囲に属することだからであって、そのジャンルに興味がなければ、多数のファンをもつような雑誌でも印象に残らないからです。 趣味と専門誌は両輪です。我が身を振り返ると、つい数年前には予想もできなかったことが起こりました。それは、1999年頃から写真に強く興味を覚え、中古カメラ店でCONTAXのコンパクトカメラを購入。2000年には一眼レフカメラを購入。2001年には、複数のカメラを購入し写真雑誌を毎月買うようになり、交換レンズも複数揃えました。 やがて2002年になると興味はカメラ本体よりもレンズに移り、カメラボディよりは高価なレンズが多数あることを知りました。興味ははっても、レンズはなかなか買えないので、代償行為としてカメラ関連の書籍を次々に読むようになりました。新刊は勿論のこと古書店でカメラ雑誌のバックナンバーや好きな写真家の写真集を買うようになっていたのです。 この原稿を書くために2002年に購入した写真およびカメラ関連の雑誌や書籍を台所のテーブルに積んでみたら、その固まりは予想を超えた量でした。趣味の領域とはいえ、その紙の山は自分の物欲を目に見えるかたちで積み上げられたようで、すこし後ろめたいような恥ずかしいような気分になってしまいました。 さて、2002年におけるカメラ関係の大きなニュースは、デジカタルカメラのますますの隆盛と、18年ぶりに登場したM型ライカのニューモデル「M7」でした。特に一眼レフ(レンズ交換可能)タイプのデジカタルカメラは各社が市場に参入したため、読者対象を一般のカメラファンに設定している『アサヒカメラ』(朝日新聞社)と『日本カメラ』(日本カメラ社)では、ほとんど毎号、M7か高級デジカメ関連の記事が掲載されつづけ、中には広告か記事か判然としないようなものも多く、かって新聞社系の写真雑誌が多数存在(※1)していた時代から遠く離れ、両誌がもはや「写真」そのものがどうこうということよりも、遅ればせながらカメラ(やレンズなど)という商品の情報誌に近づいた印象がありました。 ※1:『毎日カメラ』(毎日新聞社)。『サンケイカメラ』(産経新聞社)などがあった。 いわゆる新製品情報以外の「特集」でおもしろかったのは、『アサヒカメラ』の9月号「ポジ編」と10月号「ネガ編」に分けて掲載された「フィルム選びの極意」でした。これは10年1日のごとく掲載される「桜」や「花火」や「紅葉」の撮影方法とは違って、珍しく実用的な記事として有効であり、わたしは百瀬俊哉氏によるネガフィルムのノウハウは、さっそく活用させてもらいました。 グラビアページに掲載された写真では、有名写真家の競作特集した『アサヒカメラ』2月号の「写真家と猫」。7月号「Nude特集」に掲載された中村征夫氏の新しい水中写真シリーズになると思われる「ぷあぷあ」がよかった。『アサヒカメラ』と『日本カメラ』が、デジカメにもケミカメ(ケミカルなフィルムを使うカメラ)にも興味のあるカメラファンのための雑誌だとすると、写真そのものに焦点を当てようとしているのが、『カメラジャーナル』です。判りやすい喩えとしては「カメラ界の『本の雑誌』」でしょうか。 ごく初期の『本の雑誌』の魅力の大半は、椎名誠氏の文章にありましたが、この『カメラジャーナル』においては、主筆を務める田中長徳氏の文章と作例写真が同様の力をもっています。氏の作例写真は、少し古いカメラや中判、あるいは大判フィルムを使ったオーソドックスな風景写真であるが、文章はトリッキーで、それまでの写真家の文章とは隔絶したレトリックを駆使した文体であり、インテリジェンスやスノビズムが前面に出ることを恐れない魅力があります。カメラの歴史を背景に、一眼レフカメラの終焉とデジカメ時代の幕開けを書いた、特集「35ミリ一眼レフ 神々の黄昏」(『カメラジャーナル』105号)は、見事な文明論になっていました。 長徳氏は膨大な数のカメラおよびレンズを所有し、その歴史的価値と現在における価値を相対的に、しかも批評性の高い文章で書き続けているため、最近は、一般誌でもよく文書を目にします。ただし『カメラスタイル』(ワールドフォトプレス)や田中長徳責任編集と銘打った『季刊クラッシックカメラ』(双葉社)などにも文章と作例写真を発表しつつ、単行本も多数出版しているため、最近は、いささかの重複や毀誉褒貶があるのが気がかりです。 マニアックなカメラ雑誌には、この『カメラジャーナル』の他に、業界誌的な匂いの強い『写真工業』(写真工業出版社)や、最強のクラシックカメラ雑誌(正確には定期的に刊行されるムック)『カメラレビュー クラッシックカメラ専科』(朝日ソノラマ)があり、ここまでくると、どの書店にも置いてあるわけではありませんが、書店で見かけたならぱらぱらと眺めてみてはいかがでしょう。わたしのように、はまってしまうとなかなか抜けられなく恐れはありますが日常生活の憂さを忘れるには最適な世界です。 複数のSF専門誌が存在していた時代が夢のように思える今日この頃ですが、2003年の現在唯一のSF月刊誌が『SFマガジン』(早川書房)です。わたしは、以前新刊書評の連載をここでしていたし、なにより七〇年代から毎月読んでいる雑誌なので、この『SFマガジン』には冷静な視線を向けられません。 2年ほど前から各号毎にテーマを絞った特集が主体になって、ぐっと読みやすくなったと思います。2002年の『SFマガジン』は、3月号の「ニール・スティーブンスと新世代作家特集」。5月号「アンソロジーを編む愉しみ」。7月号の「数の迷宮へ---暗号/数学SF特集」など、粒ぞろいの特集企画が多く、毎号読み応えがあった。 連載していたことがあり、昔から読んでいるといえば『本の雑誌』も同様で、なんとなく冷静に眺められない想いがあります。スタッフや書き手に世代交代があありましたが、あいかわらず毎号、本とその周辺の話題で厭きさせません。アベレージの高い雑誌といえるでしょう。 季刊ながら『SFJapan』(徳間書店)も健闘しています。日本SF新人賞の一挙掲載などは、日本SF大賞と日本SF新人賞の主催社である徳間書店ならではの力業でしょう。豪華な対談、コミックやアニメにも目配りをした特集も毎号楽しみです。 書店によっては無料で入手できるものにPR誌と呼ばれる冊子があります。わたしは代々木上原にある幸福書房さんで、毎月、『青春と読書』(集英社)、『本の窓』(角川書店)、『本の話し』(文藝春秋)をいただいています。 これらは、それぞれ巻頭に、その月の一番の新刊に関連した工夫された企画が掲載されていることから、思いがけない関連情報が入手できることがあります。また意外に大物が連載をしているのがこれらの雑誌の売りで、わたしは『本の窓』に連載されている大島弓子さんの「グーグーだって猫である」を毎月楽しみにしています。 その他、定期的に購入し、読んでいる雑誌に『Casa BRUTUS』(マガジンハウス)、『BRUTUS』(マガジンハウス)と『BE-PAL』(小学館)があります。『BRUTUS』は月2回刊の雑誌で、毎回の特集によって大きく印象の変わる雑誌です。わたしは創刊号から、ほぼ毎号購入をつづけてきましたが、最近はまったく興味のもてない特集があり、購入しないことも増えてきました。反面、以下に挙げる特集号は、絶賛してもいい誌面作りで愉しめました。 476号「君はハンニバルを見たか!?」 486号「私たちもお茶会してもいいですか?」 489号「なぜ、ナニ?タカラヅカ!」 491号「恋する・温泉!」 492号「映画は、儲かりまっか?」 494号「もう本なんか読まない!?」 『Casa BRUTUS』は、女性誌も含め、現在もっとも洗練されたファション雑誌であり、近年の建築(建築家)ブームの推進役を担った雑誌です。「ミュージシャンズ・ミュージシャン」という言葉をご存知でしょうか、「音楽家に影響を与える音楽家」といった意味ですが、反面マニア向けという意味も含まれているようです。『Casa BRUTUS』は「マガジンズ・マガジン」といった側面があり、数々の雑誌によく真似られています。 毎号クオリティの高い誌面になっていますが、4月号の特集「World Museum Best 100」は、世界の博物館や美術館を網羅した上に、museum業界の裏側まで(品よく)暴いた内容で、他の雑誌では真似のできない圧倒的な規模とセンスでした。すべての雑誌編集者が嫉妬に身もだえたでありましょう。 バックナンバーの取り寄せという手間をかけても読む価値があります。『Casa BRUTUS』で楽しみにしているのが毎号最終頁に掲載される「Life@Pet」です。まあ早い話が有名人のペット自慢なのですが、主人の紹介とペットの「年齢と出身地」「特技」が記され、主人と一緒に写真におさまるペットの姿がなんとも和ませてくれます。 『outdoor』(山と渓谷社)の休刊により、唯一の月刊アウトドア雑誌となったのが『BE-PAL』です。一時の中断はありましたが創刊号から読んでいる雑誌のひとつです。さほどのページ数ではありませんが、軽薄さと堅実さとが見事に同居しているので、多様な読者層にアピールする構成になっています。雑誌作りのプロの凄味を感じさせる雑誌です。 わたしがやめられない悪癖に「喫煙」と「プロレス」があります。それほど頻繁に会場観戦するわけではないし、深夜のプロレス番組も毎回観てはいませんが、毎週木曜日発売の『週刊プロレス』は買うのをやめられません。これは何故かと考えると、そもそもはターザン山本氏が編集長をしていた当時の『週刊プロレス』で展開された「活字(による)プロレス」時代の熱気に遡ります。あの頃のおもしろさが強い動機づけとなっていて、今もわたしに『週刊プロレス』を毎週買わせるのです。 これは、わたしが、すでに同誌を離れて久しいターザン山本の呪に、いまだに絡め取られたままなのでしょう。 カウンターカルチャーの匂いが強い『紙のプロレス ラジカル』は、プロレスと格闘技をテーマにした雑誌ですが、毎号、人間(プロレスラー&格闘家)の凄味とトホホを上手に引き出すインタビューが売りです。 |
| 奇、奇譚、ファンタジー | ミステリー | ノン・フィクション | 雑誌編 | |
