
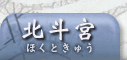
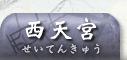
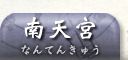



| 《第十回》 猪木引退の日に―― |
一九九八年、四月四日。 この日は、二重の意味で、ぼくにとってたいせつな日となった。 まず、この日は、アントニオ猪木の引退の日であった。 東京ドームに七万人の人間が集まり、三十八年間のプロレス生活にピリオドを打つ猪木 の試合を観戦した。 リングサイドには、モハメド・アリをはじめとして、ボブ・バックランド、前田日明、 長州力、キラー・カーン、初代タイガー・マスク佐山聡の姿もあり、しかもこの実況は、 かつて、 「藤波よ猪木を愛で殺せ」 という、背筋の毛が立ちあがるような、極めつけの名言を吐いた、古館伊知郎である。 ぼくの周囲の、プロレスからはとっくに足を洗ったような連中も、 「どうせ、参院選に出て、落ちたらまたカムバックするんだろう」 などと言いながら、 「でも、四月四日はドームに行くんだもんね――」 とチケットはしっかり手に入れたりしていたのである。 このぼくも、ゆくつもりであった。 最近、ぼくのプロレスは活字プロレスとなり、ターザン山本が『週プロ』から消えてか らは、活字プロレスもここひとつ乗り切れない状態で、もっぱら格闘技にのめり込んでい たのだが、猪木の試合を生で見るチャンスが、もしかしたらこれが最後になるかもしれな いとあっては、やはりドームにゆくつもりではいたのである。 ところが、なんと、昨年にぼくが書いた『神々の山嶺(いただき)』という本が、“日本冒険小説協会 大賞・日本長編部門”の大賞をとってしまったのである。 その授賞式が、同じく四月四日であったのだ。 この賞は、内藤陳さんが会長をやっている“日本冒険小説協会”が出している賞であり、 プロの作家や出版社が出している賞ではない。純粋に、おもしろい本の好きなファンが手 弁当で選ぶ賞であり、SFの方では星雲賞がこれにあたる。 たいへん名誉ある賞であり、作家にとっては嬉しい賞なのである。 パーティー会場――つまり宴会とどんちゃん騒ぎの場所は、熱海の某旅館であり、東京 ドームとのかけもちはまず無理である。 熱海の方にゆくことにした。 猪木の試合の方は、テレビで見ることができるのがわかっていたからである。 この賞、賞状の文面も、ありきたりのものではなく熱っぽい。 貴方はヒマラヤの峻厳な山々を背景に山の魔力に取り憑かれた男たちの狂おしいまでの 情念を描き出した本作により見事に大賞を獲得されました。 「山があるからではない。おれがいるから登るんだ」と言い切る伝説の登山家羽生の自信 と孤独。自身の存在理由を求めて羽生の足跡を追うカメラマン深町。人間たちの卑小な思 惑など遥かに超越して聳え立つ神々の山嶺エベレスト。 我々紙上冒険家に標高八千メートルの白き魔界の過酷さを体感させ得た貴方の筆力を称 え、その栄誉を賞します。 内藤陳さんが、これを読んでいるのを聴きながら、目頭があつくなってしまった。 この小説を書いている時の気分や、書きあげた時の心のたかぶりなどを思い出してしま ったからであり、作家の、あのちまちまねちねちとした、孤独な暗い作業がむくわれる現 場に、心の準備をせずに立ってしまい、あついものがこみあげてきてしまったのである。 実のところ、『上弦の月を喰べる獅子』を書きあげた時にも似たような状態になったことが あるのだが、このような話を書きあげたあと、書き手には、どうにも腰の定まらない時期 があるのである。 つまり、一度、あるレベル以上のものを書いてしまうと、次に書くもののレベルを落と せなくなってしまうのである。 少なくとも、『神々の山嶺』を書いてしまった以上は、書き出す前から、書きあがったと しても、この作品よりもレベルが落ちるとはっきりわかっている作品を、もう、書けなく なってしまったのである。書いても、おもしろみがない。 ぼくは、小説のアイデアは、無限に持っており、果たして死ぬまでにそのアイデアの全 てを書き切ることができるだろうかと、長い間悩んできた。ぼくの持っているアイデアの 量に比べたら、ぼくの寿命などゴミのように短い。 そのように考えていたのである。 しかし、『神々の山嶺』を書き終えてみたら、そうではなかった。そうではなくなってし まったのである。 もう、『神々の山嶺』よりレベルが落ちるとわかっている話のアイデアは、捨てねばなら ないことになってしまったのだ。 なんということだろう。 ぼくは、アイデアが無限にある作家から、アイデアの残量の少ない作家になってしまっ たのである。 どうしよう。 自分自身に対して、泣きを入れたくなっていたのだが、内藤陳さんが、前記の文章を読 みあげてゆく声を壇上で聴いているうちに、身の裡から力が沸いてきたのである。 自分がこれから書かねばならない話が、これまで以上にしんどい作業を経ねばならない とわかっていても、それについては、おとなしく覚悟をしなけりゃならないな、と腹がす わったのである。 なまじ、大長編を一本ぶっ書くということがどういうことか、そのディテールまできっ ちりとわかっているものだから、これから自分がやらねばならない仕事のことを思った時 ――ようするに、びびってしまっていたのですね。 これでだいじょうぶ。 書き手がむくわれるということは、間違いなくあるのであります。 というわけで、家に帰ってから、六日に猪木の試合の映像を、テレビで見たのである。 猪木の相手は、小川を下したドン・フライである。 猪木の相手は小川だろうと思っていたのだが、まさかドン・フライであったとは。 後半、猪木はかなりいい延髄斬りを入れ、コブラツイストでドン・フライに勝ってしま った。 二十八歳から三十四歳くらいまでの、最高の時期の猪木には比ぶべくもないが、五十五 歳の猪木が、あそこまで動けたことで、良しとすべきだろう。 今後、もし、猪木がカムバックする時があるのなら、それは、もう、 “猪木vs.馬場戦” でなければならない。それ以外はダメ。 じゃないと、許さんけんね。九十九パーセント、あり得ないとは思うが、残りの一パー セントを楽しみにする権利は、ファンの側にはあるだろう。 |
 |