
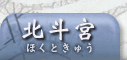
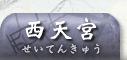
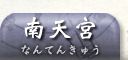



| 《第二十一回》このお金、原稿料からひいて下さい。 |
しばらく前に、ぼくの書いた『神々の山嶺(いただき)』で第十一回の柴田錬三郎賞をいただいた。 柴田錬三郎と言えば、かの眠狂四郎なる時代劇の名キャラクターをこの世に生み出した作家である。映画やテレビでも、市川雷蔵や田村正和などがこのキャラクターを演じている。 受賞の知らせをもらう四日ほど前に、編集者から電話があった。 単行本担当の方であり、雑誌編集者と違って、そういつも連絡があるわけではない。連絡がある時は、たいてい増刷のお知らせである。 しめしめ、またおれの本が増刷になったか。これでまた印税がしこたま入ってくるぞ。そうなったら、マンションのふたつみっつも買い込んで、そこに若い女の子を住まわせて――といつもの妄想がふくらんでくる。いっそ、東京ドームのプライド4のチケットを全て買い込んでくれようか。ヒクソン対高田戦を、たったひとり、おれだけで観てくれるワ。いやいや、まったくもって、作家稼業はやめられんわなあ。 そう思っているところへ、 「十月一日の夕方はどこにいますか」 と彼は言うではないか。 あら? 増刷、印税ががばがばの話ではないの。 「どうしたんですか」 とおれが訊ねると、 「ええ、ちょっと――」 と、担当者の声が口ごもるではないか。 ははーん、と、ここでおれはピンときた。 小説業界では、あちらこちらでいくつもの賞が設定されており、その賞の候補になる時にはあらかじめ連絡が入ることになっている。 たとえばこんなぐあいである。 「あなたの『お下品男爵夜の事件帳』が、このたび日本下ネタ文芸家協会のイケイケ文学大賞の候補になったのですが、受賞した場合、これをお受けいただけますか」 何故、候補の段階でこのような連絡が入るのかというと、いざ受賞が決まってから著者に連絡をすると、 「そんな賞いらんもんね」 という方が、おられるからである。 賞を出す方としては、これが一番困ることなのである。賞の権威はガタ落ちであり、もう一回別の作品を選びなおすというわけにもいかず、実にカッコの悪い、おさまりのつかないことになってしまうのである。 過去に、実際にそのようなことがあったのであり、賞を出す側としてはこのようなリスクを避けるために、候補の段階で、いかがですかと、あらかじめ作家におうかがいをたてるということになっているのである。 そうでない賞もある。 たとえば、SF作家クラブがやっているSF大賞がそうである。 候補作は、本人にも誰にも知らせない。受賞作品だけを発表する。 これは、つまり、候補作品について、選者があれこれと批評をすることになるからである。デビュー前のまだ新人ですらない書き手の応募作品ではない。プロ作家の作品を候補にし、あれこれとけなしたり、辛口の批評もする。候補作が選者の友人の作家の作品である時もあり、またある時は、先輩作家の作品や、自分よりも売れている作家の作品について、あれこれ言わねばならない時もあるのである。 これはどうもイケナイのではないか。 ということで、SF大賞は、選考会での発言は、いっさい活字にならない。受賞作品のみが語られることになっているのである。 柴錬賞も、候補作品をあらかじめ発表したり、本人に知らせたりしない賞なのである。 ただ、受賞が決まった時に、本人に連絡をとらなければいけない。 本人に連絡をとり、“いただきます”の返事をもらわないと、選考委員会の方々も帰るわけにはいかないからである。 というわけで、選考会の日、あらかじめ、本人がどこにいるかを知っておく必要があるのである。しかし、賞の候補になったからと言うわけにもいかず、“ちょっと”といったニュアンスの電話になるというわけなのであった。 そんなわけで(どういうわけなんじゃ)、九月の二十七日に、K‐1を観るため、大阪ドームへ行ってきたのである。 これについては、すでに“別の雑誌”に書いてしまっているので、ここではK‐1からの帰りにおこった悪夢のような事件について書いておきたい。 金がなくなってしまったのである。 盗まれたり、落としてしまったりしたのではない。サイフの中に金が少ししかないにもかかわらず、家を出てしまったのである。 最初にそれに気がついたのは、出発の時、小田原駅でのことであった。 大阪までのチケットを買った時に、どうも残りの金が少ないことに気がついたのだ。もしかしたら、千円か千数百円、帰りの新幹線代が足らないかもしれない。きちんと数えてる時間はなかったので、いざとなったら同行者にかりればいいと、そのまま改札をくぐってしまったのだが、車内で、同行の『スコラ』の編集者と会ったとたんに、そのことをころっと忘れてしまったのである。 思い出したのは、新大阪で帰りのチケットを買う時であった。 「あら、残りが少ししかない」 と、同行の編集者が言い出したではないか。 自動販売機で帰りの自分の分のチケットを買ったら、編集者も、残りの金が数百円しかなくなってしまったというのである。 げげっ。 あわてて調べてみたら、やはり足りない。ぼくの、小田原までの新幹線代が二千円近く不足しているのである。 「なあに、カードがあれば大丈夫ですよ」 というわけで、みどりの窓口へ出かけてゆき、カードを出したのだが、 「カードは使用できません」 と言われてしまったのである。 「あちらで、カードを現金にかえられますので……」 というので、“あちら”へゆき、機械にカードを差し込むと、画面に“暗証番号を押して下さい”との表示が出てきた。 「何ですか、この暗証番号というのは!?」 つまり、カードをひろった人間が他人のカードで金を引き出すことができないように、あらかじめ暗証番号を登録してないと、現金を引き出せないようになっているのであった。あたり前のことなのだが、五分後にはもう、東京方面行きの最終が出てしまうので、我々はもうパニックをおこしている。四〇を過ぎたいい歳のおっさんがふたりもそろって、まったくなさけない。 必殺天下のゴールドカードを、二枚も持っているのだが、こういう時は、尻もふけやしないただのゴミ同然である。 「とにかく入場券で乗ってしまいましょう」 手口は乗ってから考えることにして、我々は、発車間際の小田原停車のひかりに飛び乗ったのであった。 車内で車掌を見つけ日本社会における最終兵器である土下座をしながら、小田原駅に着いたら家の者を呼んでそこで精算しますから、 「どうぞお許し下さい」 と床へ頭をこすりつけているところへやってきたのが、前記“別の雑誌”である『フライデー』の編集者様であったのである。 地獄で仏とはこのことである。この編集者様も、K‐1の取材で大阪に来ており、帰りの車内でぼくの姿を見かけ、声をかけに来たのである。 ぼくは、さっそく、土下座の相手をかえて、 「どうかどうか、しめきり守りますから、このあわれなユメマクラめをお助け下さい」 と、床にまたもや額をこすりつけたのであった。 いやいや、ほんとにあの折は助かりました。 どうかあのおりお借りしたお金は、原稿料からひいて下さい。 |
 |