
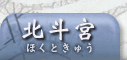
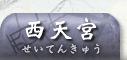
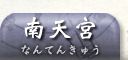



| 《第二十五回》演出の魔術 |
『百物語』という芝居のことを知っているだろうか。 日本人作家の書いた怖い短編を、女優白石加代子が一人芝居風に朗読し、鴨下信一が演出するというスタイルで、一九九二年にスタートして、現在(一九九八年)五〇話を越えた出しものである。 筒井康隆、半村良、泉鏡花、内田百閒、江戸川乱歩、三遊亭円朝等々と、錚々たる顔ぶれの作家が、その演目の作者として名を連ねている。 最終的には全部で九十九話までやってしまおうという実にとんでもない、しかし、たいへんにおもしろく興味深い試みなのである。 ぼくの話も、第一夜目にやっていただき、それがあまりにおもしろかったものだから、現在も「百物語」には足繁く通い、白石加代子の舞台の追っかけをやっているのである。 それが今回、「百物語」の番外編をやってみようということで話が盛りあがり、全て現代作家の書き下ろし作品でやることになってしまったのである。 つまり、これまでは、書き手は白石加代子に読まれるということを知らずに(あたりまえのことだけど)書いていたのだが、今回は白石加代子に読まれることを前提にして、この舞台のために作家側が作品を書き下ろすことになったのである。念のために書いておくが、舞台の脚本を書くのではなく、書くのはあくまで広い意味での小説というスタイルの怪談譚である。 十二月十一日から十八日まで紀伊国屋ホールでやることになっているのだが、すでにチケットは全て売り切れであり、これが活字になる頃には、おそらくこの舞台は終っているはずである。 阿刀田高「迷路」。 乃南アサ「夕がすみ」。 高橋克彦「母の死んだ家」。 鈴木光司「空に浮かぶ棺」。 夢枕獏「安儀橋(あぎのはし)の鬼、人をくらふ語(こと)」。 宮部みゆき「布団部屋」。 小池真理子「康平の背」。 こういうラインナップとなった。 豪華な顔ぶれであり、こういう試みは、書く側もおもしろがって、どんなに忙しかろうと、仲間はずれにされたくないものだから、ふたつ返事でOKしてしまったものと思われる。 色々他の書き手の皆さんがどういうタマを投げるのか興味もあったのだが、ぼく自身は直球、ストライクの勝負をした。 語る、という基本路線を大事にし、『今昔物語』から題材をとって、「安儀橋(あぎのはし)の鬼、人をくらふ語(こと)」という講釈風の話を一本書いたのである。 酒の席でのことなのだが、鬼が出るという橋に、行ける行けない、という話になって、結局そこまで出かけてゆく男の話である。 陰陽師が出てくるので、この陰陽師を安倍晴明にしたて、と考えていたのだが、そうすると話が長くなりそうであり、内容もばらけてしまいそうなので、予定をかえて陰陽師はただの陰陽師として話をすすめたのだが、この方がよかったと思う。 というわけで、この話の演出風景を見に、つい先日出かけて行ったのである。 原作者が、演出の現場にいるというのは、演出の鴨下さんも、これを演る白石さんも、もしかしたら、やりにくいかなとも思ったのだが、おふたりともプロ中のプロであり、ぼくの作品以外の演出現場はこれまでにも何度か覗かせてもらっているので、決心をして出かけてきたのである。 これまで見学させてもらった鴨下さんの演出現場がまたとてつもなくおもしろくて刺激的なものだから、機会があればどんなに忙しくても、なんとか時間をやりくりして通ってしまうのである。 この演出風景を、そのまま観客を入れて出しものとして見せても実におもしろいものになるだろうと思っているのだが、今回はそこまで書いているスペースはない。 この日のけいこが始まった。まず、白石さんが通しで全体の朗読をする。朗読と言ってもただ読むだけでなく、演技が入る。演技といってもひとり芝居というほどある役に入り込むわけではなく、あくまでも白石さんは、朗読者という客観的なスタンスを持ち続け朗読するわけだから、このあたりの加減がたいへんに微妙である。 つまり、白石加代子には、まず、 ①生身の白石加代子というスタンスがあり、 ②朗読者、原作者の地の文を声にしてゆくという客観的スタンスもあり、 ③さらにこの話の場合、講釈というスタイルをとっているので、講釈者という個性も演じねばならないというスタンスもあり、 ④主人公や、その相手や、彼らの仲間や、その妻たちや、鬼たちをはじめとするたくさんのキャラクターを演じてゆくというスタンスもあるのである。 たいへんに複雑な構造がここにはあるのであり、しかも、今回は、七本の同様の作品を演らねばならないのである。 これは、たぶん、普通の舞台(つまりあるひとりのキャラクターを演ずるという意味です)よりもずっとたいへんな作業であろうと思う。 ぼくだったら、気が遠くなって逃げ出してしまうところである。 白石加代子も鴨下信一も、なんという過酷なことをやっているのか。白石さんが通して読んだあとに、鴨下さんが細かい演出のチェックを入れてゆく。 「そこはね。現代でやっちゃっていいの。居酒屋でさ。サラリーマンが飲みながら上司の悪口なんか言ってるあのノリでいいの」 「そこはほら、クリントンのCMがあるじゃない。おれだったら言ってやるよ。大統領だって何だって、がつんと言ってやるよ、と言ってたら、ほんとうにクリントンが目の前にいてさ。あそこでしどろもどろになっちゃうあれでいいんだよ」 「そのふたりはね、個性を演じわけた方がいいところだね。たとえばさ、一方が身体が大きくてさ、一方が身体が小さいという設定でやってみて。一方が西田敏行でさ、一方が西村雅彦でもいいんだよ」 「ここはね。しゃべっている理屈の部分をきちんと押さえておくことが大事なんだよ。そのあとで、その理屈がすべて何の役にもたちませんでしたってことになるわけなんだから、ここはきちんとやっとかないと」 「ここは、ゆっくりとやって――」 実に細部に至るまで、鴨下さんの手が入ってゆくのである。 手の位置、扇子の位置、顔の向き、足の位置、何気ない眼の動き、それがどのようなものであれ、舞台上ではそれが意味なく存在しているものはないのである。 鴨下さんのただのひとつも言うことは、そのまま、小説作法であり、こちらが何気なく書いている場所でさえ、ああなるほど、言われてみれば、あそこはそういうつもりで書いていたのだなあ――書いている時のこちらの心の動きまで思い出してしまうのである。 どきどきするほどおもしろく、刺激的で、しかも勉強になってしまうのである。 鴨下信一の言葉に、応えてゆく白石加代子がまた凄い。 声の調子を変え、別人になり、テンションをあげ――ほとんど無限の演技の引き出しを持っているんじゃないかと思えてしまう。 演出が加えられるたびに、話に話が立ちあがってゆくのである。肉がつき、ふくらみ、立体的になってゆく。 鮮やかな魔法を眼の前に見ているようである。 そこらの才能のない役者であれば、何もできずに泣き出してしまうんじゃないかと思うようなところを、白石さんが鴨下さんの要求に応えてゆくのである。 互いに相手の器量に対する信頼関係がないととてもできるものではないだろう。 プロの最上級の仕事の現場に立ちあって、それを覗くというのはほんとに気持ちがいい。 ああ、それにしても本当に怖い。 こんな凄い人たちの中にこのぼくが混じっていていいのだろうか。 おれももっとがんばろうという力こぶのようなものが、湧いてきたのであった。 |
 |